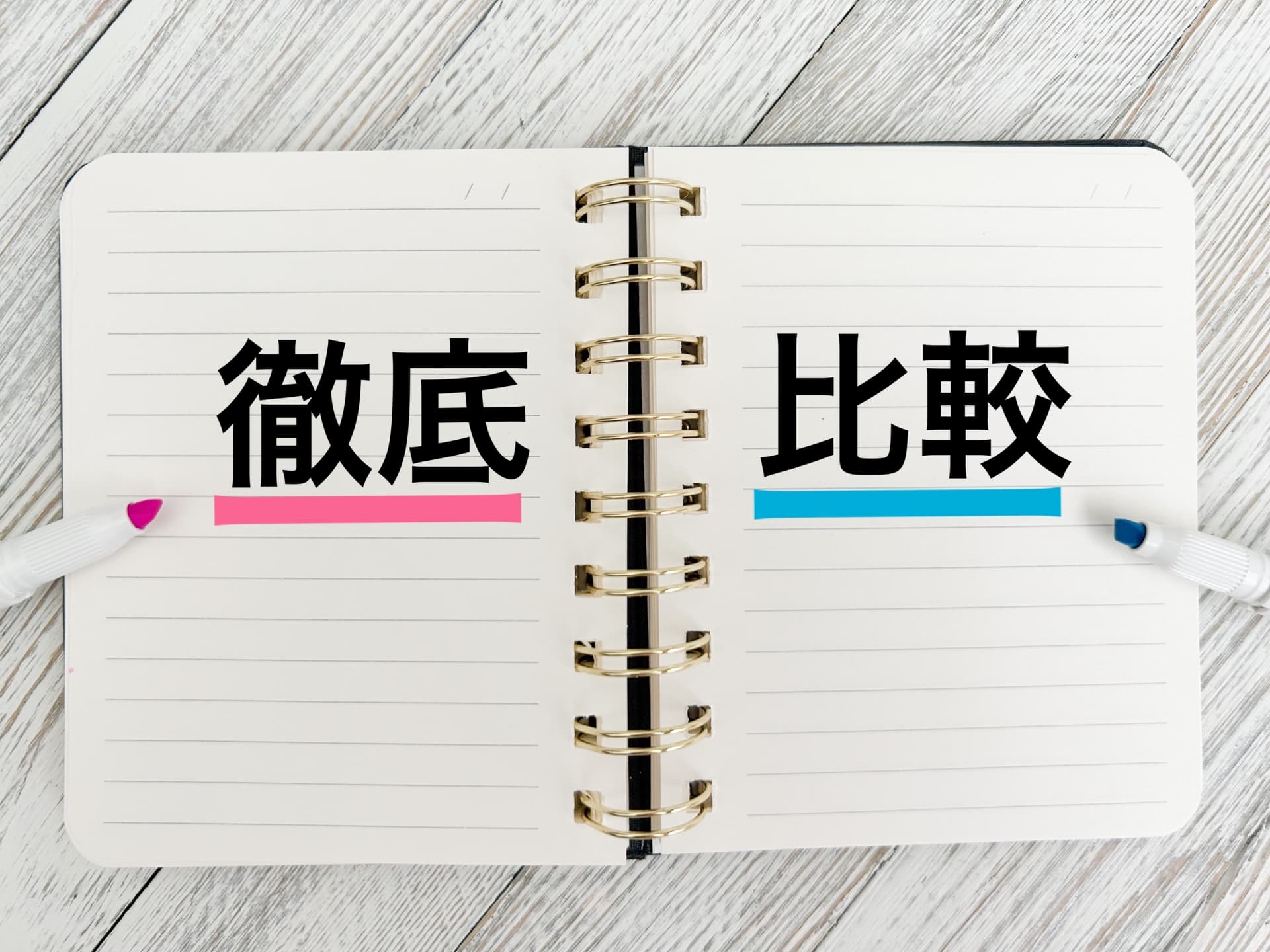なぜ今、多忙な外来クリニックこそ「往診(在宅医療)」を検討すべきなのでしょうか?
院長先生、こんなお悩みや思いを抱えていませんか?
高齢化という"不可逆な波"と、地域に根ざすクリニックの新たな使命
外来だけでは得られない「経営安定化」と「収益の柱」としての在宅医療
かかりつけ医として、患者と家族に最後まで寄り添う価値
往診と訪問診療 – 制度の違いと収益の要となる診療報酬
今さら聞けない「往診」と「訪問診療」の明確な違い
在宅医療を始めるために必要な「在宅療養支援診療所」の施設基準と届け出
収益化の鍵を握る主要な診療報酬(在宅時医学総合管理料など)のポイント
院長が在宅医療への参入を躊躇する「3つの壁」とその突破口
【壁1:収益性】「本当に儲かるのか?」に応える、超リアルな収益シミュレーション
シミュレーション結果の比較 月額収益(10名)
差額:約200,000円
【壁2:人的負担】「一人医師法人でも大丈夫?」– 週1日から始める"最小負担"スモールスタート術
【提唱】週1日・患者2人から始める"超"スモールスタート術
【壁3:24時間対応】「自分の時間はなくなるのでは?」– 最大の懸念を払拭する"仕組み"
「24時間対応の呪縛」から院長を解放する、新しい在宅医療のカタチ
これからの時代の常識 – 「自院で全てを抱え込まない」という発想
夜間・休日の緊急コールは「連携」して乗り越える – 機能強化型在支診という選択
具体策:医師の負担を減らす「バディ往診」という賢いソリューション
【バディ往診の活用イメージ】
明日からできる!在宅医療導入に向けた具体的な5ステップ・アクションプラン
院長の未来と、クリニック経営の新たな可能性を拓くために
夜間オンコール代行サービスなら
「バディ往診」がおすすめ
※この記事の情報は掲載開始日時点のものとなります
※掲載内容は予告なく変更されることがありますのでご了承ください